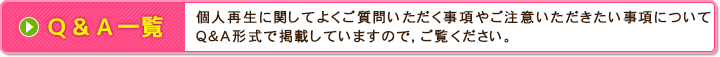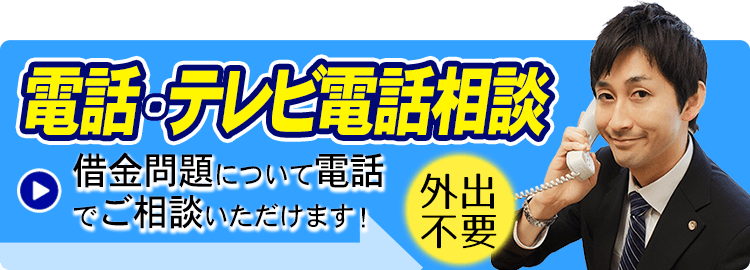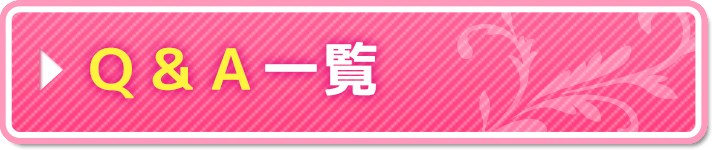お役立ち情報
個人再生をすると退職金はどうなるのか
1 退職金によって返済額が変わる可能性がある
個人再生の場合、自己破産とは異なり、強制的に資産を取り上げられるということは基本的にありません。
そのため、退職金を強制的に持っていかれてしまうということもありません。
その代わり、個人再生として債権者に支払っていく金額に、この退職金が上乗せになるという可能性があります。
では、どのような場合に上乗せされるのか、上乗せされる場合どのように計算するのか、ここでは解説していきましょう。
2 個人再生における支払い基準
個人再生において、手続き後に債権者に支払う金額の基準は、①最低弁済基準②清算価値基準③可処分所得基準、の3つがあり、このうち②の清算価値基準が適用された場合に「退職金」の金額が関係してきます。
まずは、簡単にそれぞれの基準の考え方を見ていきましょう。
① 最低弁済基準
借入額の合計から、個人再生として支払っていく金額を計算するもので、具体的には以下のとおりです。
| 借入額の合計 | 支払う金額 |
| ~100万 | 借金の金額そのまま |
| 100万~500万円 | 100万円 |
| 500万~1500万 | 借入額の合計の5分の1の金額 |
| 1500万円~3000万円 | 300万円 |
| 3000万円~5000万円 | 借入額の合計の10分の1の金額 |
※5000万を超える場合、個人再生手続きはそもそも使えません。
② 清算価値基準
お手持の資産の合計額から、個人再生として支払っていく金額を算定するという方法になります。
具体的に計上される資産とは、現金、預金、保険の解約返戻金、不動産、自動車、そして、「退職金」、等々です。
③ 可処分所得基準
ご自身の給与から、社会保険料や税金を差し引いた、いわゆる「手取り」の2年分を算定するという方法で、他の二つの方法よりも高額になる可能性が高いです。
3 清算価値基準が適用される場合
前述の通り、退職金を考慮しなければならないのは、上記②の清算価値基準が適用される場合になりますが、どのような場合に清算価値基準が適用されるのでしょうか。
個人再生には、「小規模個人再生」というものと、「給与所得者再生」というものの2種類があります。
小規模個人再生の場合には上記①~②のうち、最も高い金額のものが、給与所得者等再生の場合には①~③のうち、最も金額の高いものが最終的な個人再生として支払っていく金額として計算されます。
つまり、退職金を含む資産の合計額が、最低弁済基準や可処分所得基準よりも高額になる場合には、退職金の金額が支払総額に影響することになります。
4 退職金の計算方法
では、清算価値基準が適用される場合、退職金はどのような計算をして資産として計上されるかを見ていきます。
実際は、裁判所により細かな運用が異なるため、ここではおおよその考え方を記載しているとお考えください。
① しばらく退職する予定がない場合
このような場合は、現在退職したとしたら受け取ることができる金額の、「8分の1」を資産として計上します。
② 退職日が決まっており、受取り予定日も決まっているが、まだ受領はしていない場合
このような場合は、受取り予定の金額の、「4分の1」を資産として計上します。
③ 既に退職しており退職金を受領済みの場合
このような場合、退職金はすでに現金・預金になってしまっているため、全額が資産として計上されることになってしまいます。
5 確定拠出型年金
会社によっては、退職金の代わりに、確定拠出型年金を導入しているところもあるかと思います。
この場合、確定拠出型年金は差し押さえ禁止財産として規定されていることから、清算価値には計上されません。
6 詳細は弁護士にご相談ください
以上をまとめると、個人再生において、退職金自体を回収されることはありません。
しかし、清算価値基準が適用される場合、退職金が資産として計上され、個人再生として支払う金額に影響することになります。
どの基準が適用されるのかは個々人の状況により異なりますし、また清算価値基準になるとしても、退職金がどのように計上されるのかは、その時の状況や、裁判所の運用によっても異なります。
よって、退職金があり、個人再生を検討されている方は、弁護士に相談することをおすすめいたします。
個人再生後の生活で気をつけるべきこと 個人再生によるブラックリストの掲載期間